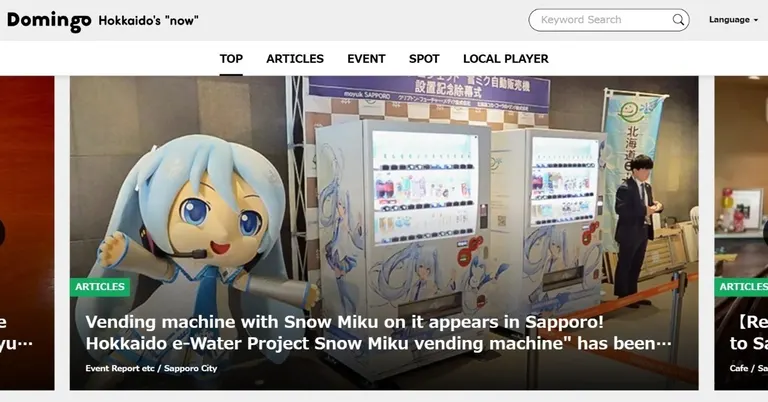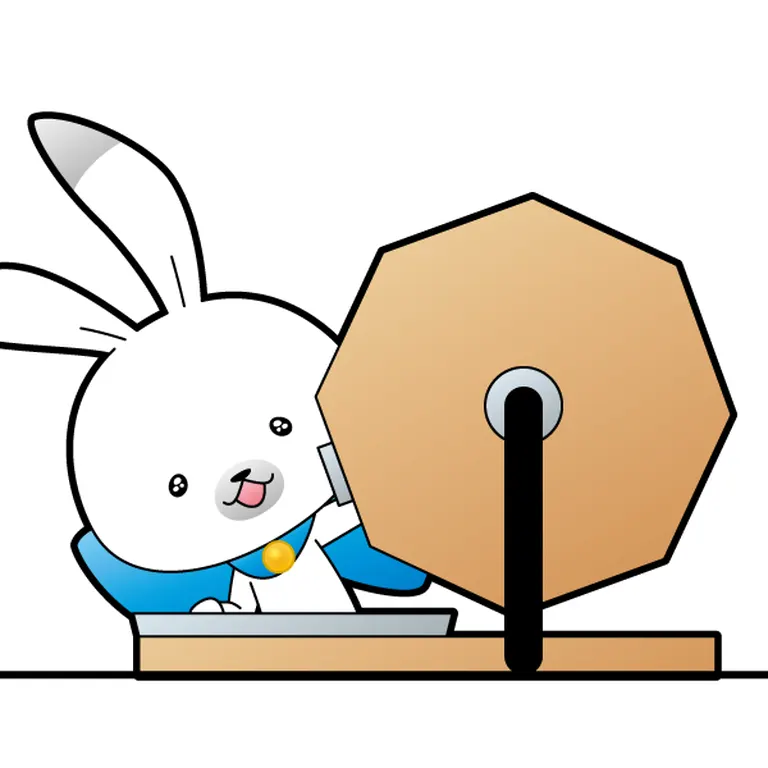お知らせ
『おクジラさま ふたつの正義の物語』間もなく公開!札幌出身の映画監督・佐々木芽生さんのインタビュー!
2017.09.28
Domingoでは今後、北海道にゆかりのある方々や北海道でイベントを開催する方々のインタビューをお届けしていきます。第1弾は、和歌山県太地町を舞台としたクジラ・イルカ漁をテーマにした映画『おクジラさま ふたつの正義の物語』の監督・佐々木芽生さんが登場!
佐々木さんは札幌出身で、現在アメリカ・ニューヨーク在住。海外に渡ったきっかけ、映画を撮影するようになったきっかけ、10/14から札幌で公開される『おクジラさま ふたつの正義の物語』の見どころ、ニューヨーカーから見た北海道の魅力などをお伺いしました。
佐々木さんは、北海道札幌市生まれの監督・プロデューサーで1987年よりニューヨーク在住。ジャーナリストとしてテレビの報道番組の取材・制作に携わった後、2008年に初の監督作品『ハーブ & ドロシー 』を完成。2016年秋に、第三作目にあたる長編ドキュメンタリー映画『おクジラさま~ふたつの正義の物語』を完成させ、2017年9月から日本全国で公開(北海道での上映は10月14日から)されています。その佐々木さんが9月19日に来札したタイミングで、お話を伺いました。
佐々木さんは札幌市出身で、高校時代まで札幌にいらっしゃったんですよね。
「私が育った札幌の家の裏に、インターナショナルスクールがあったんです。今の札幌ドームの近くだったんですが、その学校の外国人の子供たちと凄く仲が良くて、いつもその子たちと遊んでいたんですよ。彼らの家に行くと、シナモンの匂いとかするじゃないですか、日本の家はお醤油の匂いとかするんですけど(笑)。ハロウィンパーティーがあったり、海外に対する凄い憧れがあったんですよね」
海外に行くことを見越して、東京の大学に進学されたんですか?
「実は、高校時代にアメリカの高校に留学したんですよ、交換留学生で。で、行った先がアメリカの物凄い田舎で、もうアメリカは二度と嫌だと思ったんですよね」
それが、大学を卒業されて1987年からは念願叶ってニューヨークの方へ行かれました。
「そうなんです。でもニューヨークに着く前に、インドに行っていたんですよ。東京の仕事を2年ちょっとくらいで辞めて、インドへ行きました。ヨガをやっていたこともあって、インドは凄く大好きで興味があったんです。もともとは3週間くらいの予定が、結局4ヶ月になっちゃって…。それで、ニューヨークの友達を頼って、ニューヨーク経由で東京に帰るつもりだったんですけど、そこでスタックしました。もう20ドルしか持ってなかったんですよ、ニューヨークに着いた時には(笑)。だからまだ、帰国の途中なんですよ、インドからの」
当時のニューヨークの魅力は、どのようなものだったんですか?
「やっぱり、自分らしく生きられるってことですね。法律にさえ触れなければ、何をやっても許されるというか。あとは、性別・年齢・国籍…そういうもので一切差別されないことです。その人の才能・実力で評価してくれるっていう部分が素晴らしいなと思いますね」
佐々木さんの場合は、ニューヨークに行かれても日本の媒体にもレポーターとして出られて、日本との関係が切れてないのが凄いなと思いました。海外に住んでいる日本人の中には、完全に向こうに溶け込もうとする人も多いので。
「最初はそういう所があったかもしれないですね。『日本人じゃなくてニューヨーカーとして生きるんだ』みたいな。私の場合は、仕事こそNHKやTBSとしていましたけど、生活そのものは全然日本と関係なく暮らしていました。1作目の『ハーブ&ドロシー』を作った時も、最初はアメリカで公開されて賞もいただいても『日本人の映画監督』ということを一言も言われないんですよ。そういうところもニューヨークは凄いなと思いました。でも、日本で2010年に『ハーブ&ドロシー』が公開された時に、凄く日本の方に助けていただいて。それからですね、日本によく帰ってくるようになったのは。実は、それまで日本のことに全く無関心でしたし、日本で何が起きているかということも全然知らなかったんです。今は1ヶ月おきくらいに日本に帰ってきています」
佐々木さんはテレビの報道番組のレポーターをされていましたが、そこから映画を撮ろうと思ったきっかけは何だったんですか?
「やっぱり『ハーブ&ドロシー』なんですね。NHKの仕事をしている時に『ハーブ&ドロシー』の話を聞いて凄い感動してしまって。この二人の話を何とか世界に伝えたいと思って、それがたまたまドキュメンタリー映画だったという感じです。『映画が大好きで子どもの頃から映画監督になりたくて…』みたいなことは一切ないので、映画監督を夢見ている方には申し訳ないんですけど(笑)」
テレビの報道番組だけでこの物語を伝えるのではなく、国を超えて伝えられる映画という存在が、延長線上にあったという感じでしょうか。
「そうですね。テレビ局に提案してみようとも思ったのですが、二人を取材しようと思った時点ではもうコレクションもしていませんでしたし、『今なぜこの二人を撮らなきゃいけないのか』みたいな所がテレビにはあって。そして、テレビだとそれぞれの番組の“枠”があるので、その“枠”にはまるような物語にしなきゃいけないですよね。だからこそ、自由に伝えるためにはドキュメンタリー映画だったらできるのかなと思いました」
- 1
- 2